この記事の要約
本記事は、自然栽培セミナー第10回の内容をもとに、
無肥料で栽培を続けても、なぜ土壌ミネラルが枯渇しないのか
というテーマについて学んだことをまとめたレポートです。
従来の農学では、収穫によって養分が持ち出される以上、
土壌中の栄養は減少していくという考え方が基本になってきました。
本セミナーでは、この前提に対して、
実際の水田や畑の土壌データをもとに検討が行われました。
慣行栽培と自然栽培の土壌を比較すると、
無肥料であっても高収量を維持している自然栽培圃場では、
リン・カリウム・カルシウム・マグネシウムといった
土壌ミネラルの含有量が低下していないケースが確認されています。
また、無肥料栽培を30年続けた圃場を調べても、
栽培年数と土壌ミネラル含有量との間に、
明確な相関関係は見られませんでした。
これらの結果から、
土壌ミネラルの状態は年数そのものよりも、
CEC(陽イオン保持力)や土壌pHといった
土壌の性質によって大きく左右されていることが示されました。
さらに、リンについては、
鉱物由来、有機物由来、菌根菌など、
複数の供給経路が関わっている可能性が示されており、
単純な含有量だけでは捉えきれない側面があることも確認されています。
本記事では、
自然栽培の土壌で起きている栄養塩供給を、
「肥料を与える・与えない」という二択ではなく、
土壌の中で循環が自律的に回る仕組みとして捉え直し、
現時点で分かっていることと、まだ分かっていないことを整理しました。
このレポートは、
自然栽培セミナー全15回を「もちまる視点」で追いかける連載企画の第10回です。
▼ この連載をまとめて読む
→ もちまる自然栽培セミナー・全話まとめガイドはこちら
https://sanseitohow.com/natural-farming-series-2/
はじめに
本記事は、自然栽培セミナー第10回の内容をもとに、
「土壌ミネラルは無肥料でも枯渇しないのか」という視点からまとめたレポートです。
前回のセミナーでは、窒素について、空気中から供給される仕組みや、土壌微生物を介した循環の話を学びました。
その流れを踏まえると、次に気になってくるのが、リンやカリウム、カルシウム、マグネシウムといった土壌ミネラルのことです。
窒素と違い、これらの元素は空気中に無限に存在しているわけではなく、主な供給源は土壌中の鉱物です。
そう考えると、作物を収穫し続ける以上、いずれは土壌から持ち出され、枯渇してしまうのではないか、という疑問が自然に浮かんできます。
では、その疑問はどのように整理されているのか。
無肥料が前提となる自然栽培で、なぜ長期間にわたり高収量が維持できているのか。
本記事では、断定的な結論を急ぐのではなく、
現時点で分かっていることと、まだ分かっていないことを切り分けながら、
セミナーで紹介された事例をもとに、自然栽培の土壌で何が起きているのかを、もちまる視点で見取り図にしていきます。
前後ナビ
[ ← 前回レポート ]
第9回「無肥料なのに、なぜ差がつく?自然栽培土壌の『窒素循環』を学んだ日」
https://sanseitohow.com/natural-farming-nitrogen-cycle/
[ 次回レポート → ]
第11回「自然栽培の現状と未来。経営の視点から持続可能性を学んだ日」
https://sanseitohow.com/natural-farming-sustainability-management-11/
「肥料で補う」農学と、「枯渇する」という前提
農業の基本的な考え方として、
「作物が育つのは、肥料として与えた養分を吸収しているからだ」
という見方があります。
化学肥料を例にすると、
土壌に投入されるのは、主に次のような成分です。
- 窒素(NH₄⁺、NO₃⁻)
- リン(P₂O₅)
- カリウム(K₂O)
- カルシウム(CaO)
- マグネシウム(MgO)
これらが土壌に与えられ、
作物が吸収し、茎や葉、実をつくる。
そして、収穫によって作物は圃場の外へ持ち出されます。
この流れを前提にすると、
次のような整理が成り立ちます。
作物として持ち出された分の養分は、
確実に農地から失われている。
したがって、減った分は外部から補給しなければならない。
この考え方は、
従来の農学の中で長く共有されてきました。
実際、
「生産物が農場外へ出ていく以上、養分は必ず減る」
「土壌の肥沃度を維持するには、肥料による補給が不可欠である」
という整理は、直感的にも理解しやすいものです。
この前提に立てば、
- 肥料を与えない栽培を
- 長期間続けることは不可能
という結論になるのも、自然な流れだと言えます。
一方で、
自然界の生態系に目を向けると、
必ずしも毎年、外部から肥料が投入されているわけではありません。
森林や草原では、
人の手による施肥がなくても、
植物は世代を超えて育ち続けています。
この違いについては、
一般に次のように説明されてきました。
自然界では、実や有機物が外部に持ち出されない。
だから無肥料でも成立している。
収穫を前提とする農業とは、条件がまったく異なる。
こうした考え方を背景に、
農学の多くの研究は、
- 肥料をどれだけ与えるか
- 与えた養分を、作物がどう吸収するか
という点を中心に進められてきました。
その結果、
土壌中に存在する鉱物から、
- どれくらいの量が
- どのくらいの時間スケールで溶け出し
- 作物に供給されているのか
といった部分については、
あまり注目されてこなかった側面があります。
しかし、自然栽培では、
この「肥料で補う」という前提そのものが置かれていません。
それにもかかわらず、
無肥料での栽培が長期間続き、
中には高い収量を維持している圃場も存在しています。
では、
収穫による持ち出しが続いているにもかかわらず、
土壌中のリンやカリウム、カルシウム、マグネシウムといった
ミネラルは、本当に減り続けているのでしょうか。
次章では、
この素朴でありながら核心的な問い――
「無肥料でも、土壌ミネラルの供給は続くのか?」
という点について、
実際の土壌データをもとに見ていきます。
無肥料でも続く?土壌ミネラル供給という問い
前章で見てきたように、
従来の農学では、作物の収穫によって養分が持ち出される以上、
土壌中の栄養は減っていく、という考え方が基本になっています。
この前提に立てば、
- 肥料を与えない栽培を
- 長期間続けることは難しい
という結論になるのも、自然な流れです。
ただ、前回のセミナーで扱った窒素の話を思い返すと、
この整理がそのまま当てはまらない場合があることも見えてきました。
窒素は、
土壌中の鉱物として存在しているわけではありませんが、
大気中に大量に存在しており、
条件が整えば、窒素固定細菌によって継続的に供給されます。
窒素については、
「持ち出される=減っていく」
という単純な図式では説明できない循環が存在している。
では、
リンやカリウム、カルシウム、マグネシウムといった
いわゆる「土壌ミネラル」はどうなのでしょうか。
これらの元素は、
- 空気中から供給されるわけではなく
- 主に土壌中の鉱物として存在している
という点で、窒素とは性質が異なります。
しかも、その多くは水に溶けにくい形で存在しており、
作物が直接吸収できるのは、
鉱物から溶け出した、ごく一部だけです。
そう考えると、
次のような疑問が自然に浮かんできます。
鉱物から溶け出す量よりも、
作物が吸収し、収穫によって持ち出される量の方が多ければ、
土壌ミネラルはいずれ枯渇するのではないか。
この点について、
自然栽培を実践している側からは、
- 「長年無肥料でも問題なく作り続けている」
という現場の声が聞かれる一方で、
理論的には「どこまで持つのかは分からない」という印象も残ります。
実際、
肥料投入を前提とした慣行栽培の枠組みでは、
- 土壌鉱物から
- どの程度の量が
- どのくらいの時間スケールで溶け出し
- 作物に供給されているのか
といった点については、
あまり詳しく検証されてきませんでした。
そのため、
「無肥料でもミネラル供給は続くのか」
という問いは、
肯定するにしても、否定するにしても、
感覚的な議論になりやすい側面があります。
今回のセミナーでは、
この問いに対して、
理屈や印象ではなく、
実際の土壌データをもとに考えていく
というアプローチが取られていました。
まず示されたのは、
- 慣行栽培の水田
- 自然栽培の水田(高収量・低収量)
それぞれにおける、
土壌中のミネラル含有量を比較したデータです。
次章では、
その実測結果を手がかりに、
「無投入であるはずの土壌で、何が起きているのか」を、
一つずつ確認していきます。
実測データで見る水田土壌のミネラル含有量
今回のセミナーでは、
まず実際の水田土壌を分析したデータが示されました。
比較されたのは、次の3種類の水田です。
- 自然栽培・低収量水田
- 自然栽培・高収量水田
- 慣行栽培水田
それぞれについて、
栽培期間中に複数回、
土壌中のミネラル含有量が測定されていました。
リン(P₂O₅)の含有量
最初に示されたのは、リンのデータです。
リン(P₂O₅)含有量の推移(mg / 100g土壌)
- 自然栽培・低収量水田:比較的高い値で推移
- 自然栽培・高収量水田:栽培途中で大きく減少
- 慣行栽培水田:中間的な推移
この結果を見る限り、
リンについては、
含有量の多寡と収量が単純には対応していないように見えます。
低収量水田でリンが多く残っているのは、
必ずしも「十分に供給されている」状態とは限らず、
作物が吸収しにくい形で存在している可能性も考えられます。
一方で、高収量水田では、
土壌中のリン含有量は低いものの、
稲体中のリン含有量は多い、というデータも示されていました。
このことから、
土壌中のリンが少ないからといって、
作物のリンが不足しているとは限らない
という点は、少し印象に残りました。
カリウム(K₂O)の含有量
次に、カリウムのデータです。
カリウム(K₂O)含有量の推移(mg / 100g土壌)
- 自然栽培・高収量水田:高い値を維持
- 慣行栽培水田:中程度で推移
- 自然栽培・低収量水田:栽培期間中に大きく低下
カリウムについては、
収量との関係が比較的はっきりしているように見えました。
特に、
無肥料であるにもかかわらず、
自然栽培の高収量水田で
高い含有量が維持されている点は、
直感とは少し異なる結果です。
マグネシウム(MgO)・カルシウム(CaO)の含有量
同様の傾向は、
マグネシウムやカルシウムでも見られました。
マグネシウム・カルシウム含有量の傾向
- 自然栽培・高収量水田
- 慣行栽培水田
- 自然栽培・低収量水田
この順で、含有量が高い状態が保たれていました。
いずれの元素についても、
毎年肥料を投入している慣行栽培より、
無投入の自然栽培水田の方が
高い含有量を示している点は共通しています。
データから見えてくること
これらのデータをまとめて眺めると、
少なくとも次のような点は言えそうです。
- 無肥料であっても、
高収量の自然栽培水田では
土壌ミネラルの含有量が低下していない - 収穫による持ち出し量が多くても、
ミネラルが一方的に減っていく様子は見られない
「無肥料=栄養が減り続ける」
という単純な図式では、
この結果は説明しきれないように感じました。
では、
なぜ無投入にもかかわらず、
土壌中のミネラル含有量が維持されているのでしょうか。
次章では、
カリウムを例に取りながら、
土壌中での供給と保持の仕組み――
特に CEC(陽イオン保持力) という考え方を軸に、
この現象をもう一段掘り下げていきます。
なぜ減らないのか?カリを例に見る供給と保持の仕組み
前章では、
無肥料にもかかわらず、
自然栽培の高収量水田では、
土壌中のミネラル含有量が低下していない、
というデータを見てきました。
では、
なぜそのようなことが起きているのでしょうか。
この点を考えるために、
セミナーでは カリウム を例に、
土壌中で起きている仕組みが整理されていました。
カリは「使われて終わり」の栄養ではない
まず押さえておきたいのは、
土壌中のカリウムには、
いくつかの存在形態がある、という点です。
簡単に整理すると、
次のような流れで存在しています。
- 土壌鉱物の結晶として存在するカリ
- 鉱物から少しずつ溶け出し、水に溶けたカリ
- 作物に吸収され、収穫とともに持ち出されるカリ
このうち、
作物が直接利用できるのは、
水に溶けた状態のカリだけです。
一方で、
土壌中には、
まだ作物が吸収できない形のカリが、
鉱物として大量に存在しています。
カリは、
「一度使われたら終わり」
という存在ではなく、
鉱物から少しずつ供給され続けている。
この点が、
従来の「減っていく」というイメージと、
少し違うところかもしれません。
カリ含有量を決めている3つの要素
セミナーでは、
無肥料土壌におけるカリ含有量は、
次の3つの要素のバランスで決まる、
と整理されていました。
- 非交換性カリ(鉱物由来)からの供給
- 土壌がカリを保持する力
- 作物による吸収(持ち出し)量
ここで重要なのは、
「吸収された量」だけを見ていても、
土壌中の状態は説明できない、という点です。
CEC(陽イオン保持力)という考え方
この章のキーワードになるのが、
CEC(陽イオン保持力) です。
CECとは、
土壌が陽イオン(カリ、カルシウム、マグネシウムなど)を
一時的に保持できる力を表す指標です。
土壌中の腐植は、
マイナスの電荷を帯びており、
水に溶けたカリ(K⁺)を引き付けます。
水に溶けたカリは、
すぐに流れてしまうのではなく、
いったん土壌中に保持され、
そこから作物に供給される。
この「一時的な貯蔵庫」があることで、
カリは地下水へ一気に流亡せず、
作物が利用できる形で循環します。
「減るかどうか」は、供給と保持のバランス
ここまでを整理すると、
土壌中のカリ含有量は、
- 鉱物からどれだけ供給されるか
- CECによってどれだけ保持されるか
- 作物がどれだけ吸収するか
この3つのバランスで決まります。
もし、
- 供給量よりも
- 吸収・流亡の方が大きければ
確かに、
いずれは枯渇に向かうでしょう。
しかし、
自然栽培の高収量水田では、
鉱物からの供給量と、CECによる保持が、
作物の吸収量を上回っている
可能性が示唆されていました。
その結果として、
無肥料でも含有量が維持されている、
と考えることができます。
それでも残る「年数」の疑問
ここで、
もう一つの疑問が浮かんできます。
鉱物からの供給が続くとしても、
それは、どれくらいの期間、
持続するのだろうか。
非交換性カリは、
理論的には有限です。
栽培年数が増えれば、
いつかは枯渇するのではないか、
という疑問は残ります。
次章では、
この「年数」という視点から、
無肥料栽培を続けた年数と、
土壌中のミネラル含有量の関係について、
実際の調査データを見ていきます。
栽培年数と土壌ミネラルは本当に無関係だった
前章では、
カリウムを例に、
土壌中では「供給」と「保持」が同時に起きていることを見てきました。
ただ、ここでどうしても残る疑問があります。
鉱物からの供給が続くとしても、
それは何年くらい持つのだろうか。
栽培年数が増えれば、やはり枯渇に向かうのではないか。
この疑問に答えるために、
今回のセミナーでは、
無肥料で栽培を続けた年数と、土壌ミネラル含有量の関係
を調べたデータが紹介されました。
無肥料栽培「年数別」の土壌分析
調査は、
関東から東北にかけての自然栽培農家から土壌を集め、
無肥料栽培 1年目から30年目 までの圃場を対象に行われています。
分析されたのは、次の元素です。
- リン
- カリウム
- カルシウム
- マグネシウム
調査前の段階では、
次のような予想が立てられていました。
無肥料で収穫を続ければ、
年数が経つほど、
土壌中のミネラル含有量は
徐々に低下していくのではないか。
これは、
これまでの農学的な前提から見ても、
ごく自然な予想だったと思います。
予想と異なった調査結果
ところが、
実際にデータを並べてみると、
意外な結果が見えてきました。
栽培年数と、
土壌中のリン・カリウム・カルシウム・マグネシウム含有量との間に、
明確な相関関係は見られなかった。
年数ごとに多少のばらつきはあるものの、
- 年数が長いほど減っていく
- 一定年数を超えると急激に下がる
といった 枯渇方向への一貫した傾向 は、
少なくとも30年のスケールでは確認されなかった、
という結果でした。
「持ち出し量」は決定的な要因ではなかった
この結果から読み取れるのは、
少なくとも次の点です。
- 作物による吸収量(=持ち出し量)は
- 土壌中のミネラル含有量を
- 単純には決定していない
つまり、
「収穫によって持ち出されるから、
年数とともに必ず減っていく」
という図式は、
そのままでは当てはまらない、
ということになります。
ここで重要なのは、
「減らない理由が完全に分かった」という話ではない点です。
この章で示されたのはあくまで、
少なくとも30年レベルでは、
年数そのものが枯渇の要因にはなっていなかった
という事実です。
では、何がミネラル量を決めているのか
年数が直接の要因でないとすると、
次に気になってくるのは、
「では、何が土壌ミネラルの量を決めているのか」
という点です。
同じ無肥料、
同じような年数であっても、
圃場ごとにミネラル含有量には違いがあります。
セミナーでは、
その違いを説明する鍵として、
- CEC(陽イオン保持力)
- 土壌pH
という2つの要素が、
強く関係していることが示されていました。
次章では、
土壌の栄養塩環境が、
栽培年数ではなく、
CECやpHとどのように結びついているのかを、
データをもとに見ていきます。
CECとpHが決めていた、土壌の栄養塩環境
前章では、
無肥料栽培を30年続けた場合でも、
土壌ミネラルの含有量が、
年数とともに一方向へ減っていくわけではない、
という結果を見てきました。
では、
栽培年数が決定的な要因ではないとすると、
何が土壌中の栄養塩環境を左右しているのでしょうか。
今回のセミナーでは、
その鍵として、
CEC(陽イオン保持力) と 土壌pH
という2つの要素が示されていました。
CECと栄養塩含有量の関係
まず示されたのは、
土壌中のミネラル含有量と、
CECとの関係を見たデータです。
縦軸に栄養塩の含有量、
横軸にCECを取って比較したところ、
元素ごとに、はっきりとした違いが見られました。
- カリウム:CECとの関係はやや弱い
- リン・カルシウム・マグネシウム:CECとの関係が強い
特に、
リン、カルシウム、マグネシウムについては、
CECが高い土壌ほど、
含有量も高くなる傾向が確認されています。
栽培年数よりも、
土壌が「どれだけ保持できるか」という性質の方が、
栄養塩含有量に強く影響していた。
この結果は、
「時間が経てば減る」という見方よりも、
土壌の状態そのものが重要であることを示しています。
pHと栄養塩含有量の関係
次に示されたのが、
土壌pHと、ミネラル含有量の関係です。
こちらも、
縦軸に含有量、
横軸にpHを取って整理されていました。
結果として、
- カリウム:明確な相関は見られない
- リン・カルシウム・マグネシウム:
土壌が中性に近づくほど含有量が増える
という傾向が示されていました。
このことから、
土壌の酸性・中性といった状態が、
栄養塩環境に大きく関係していることが分かります。
なぜpHがCECに影響するのか
ここで、
pHとCECの関係についても説明がありました。
土壌中の腐植は、
マイナスの電荷を帯びており、
陽イオンを吸着する性質を持っています。
しかし、
土壌が強く酸性に傾くと、
水素イオン(H⁺)が増え、
腐植の結合部位を占有してしまいます。
- pHが低い状態:
H⁺が多く、CECが低下しやすい - pHが高い状態:
H⁺が少なく、CECが高まりやすい
土壌のpHは、
CECを通じて、
栄養塩を「保持できるかどうか」に影響している。
このような関係が、
データからも裏付けられていました。
化学肥料と土壌酸性化の話
ここで、
化学肥料が土壌を酸性化させる仕組みについても、
簡単な説明がありました。
例えば、
よく使われる窒素肥料(硫酸アンモニウム)は、
土壌中で分解される過程で、
水素イオンを増やす方向に働きます。
その結果、
- 土壌pHが下がる
- CECが低下しやすくなる
- 栄養塩が保持されにくくなる
という流れが生じやすくなります。
自然栽培では、
化学肥料を投入しないため、
一度pHを整えておけば、
大きく酸性に傾きにくい、
という点も指摘されていました。
pHとCECは「年数よりも強い要因」
ここまでの話を整理すると、
今回のデータから見えてきたのは、
- 栽培年数そのものよりも
- 土壌pHやCECといった
「土壌の性質」の方が
土壌中の栄養塩含有量に、
強く影響している、という点です。
年数を重ねても、
pHとCECが保たれていれば、
ミネラル環境は必ずしも悪化しない。
逆に、
年数が浅くても、
pHが低く、CECが小さい土壌では、
栄養塩が不足しやすくなる。
そんな構図が、
少しずつ浮かび上がってきました。
それでも残る「リンの違和感」
ただし、
ここまでの整理でも、
ひとつ引っかかる点が残ります。
それが、
リンの挙動です。
リンは、
- 土壌中の含有量は低い場合がある
- それでも作物中のリン含有量は多い
といった、
他のミネラルとは少し異なる振る舞いを示していました。
次章では、
このリンに焦点を当て、
「リンはどこから、どのように供給されているのか」
という点を、
複数の経路に分けて整理していきます。
リンはどこから来るのか?4つの供給経路
前章までで、
CECやpHが土壌ミネラル環境に大きく関わっていることが見えてきました。
しかし、
リンについては、
他のミネラルとは少し違った振る舞いをしているように感じられます。
土壌中のリン含有量は低いのに、
作物中のリン含有量は必ずしも低くない。
この点は、
これまでの整理だけでは説明しきれません。
そこで今回のセミナーでは、
自然栽培におけるリンの供給経路 が、
いくつかに分けて整理されていました。
リンの供給経路①:難溶性リンからの溶出
土壌中のリンの多くは、
鉱物に結合した 難溶性リン として存在しています。
このリンは、
そのままでは作物が吸収できませんが、
時間をかけて少しずつ溶け出し、
水に溶けたリン酸の形になります。
- 鉱物として存在
- 徐々に可溶化
- 植物が吸収できる形へ
という、
比較的ゆっくりとした供給経路です。
リンの供給経路②:有機物由来のリン
もう一つの経路が、
作物残さや有機物に含まれるリンです。
作物が枯れたり、
残さが分解されたりする過程で、
有機物中のリンが分解され、
可溶性のリン酸として土壌中に供給されます。
- 作物 → 残さ
- 微生物による分解
- リン酸として再供給
という循環が、
この経路にあたります。
リンの供給経路③:菌根菌を介した供給
自然栽培の文脈でよく話題に上がるのが、
菌根菌 の存在です。
菌根菌は、
作物の根に共生し、
菌糸を土壌中に広げてリンを吸収します。
その代わりに、
菌根菌は作物から炭素(エネルギー)を受け取り、
共生関係を保っています。
ただし、
セミナーでは、
この点について慎重な説明がされていました。
菌根菌は確かにリンを運ぶが、
どの程度、作物のリン吸収に貢献しているかは、
現時点でははっきりしていない。
また、
菌根菌は菌類であるため、
水田のような嫌気的な環境では、
十分に機能しにくいという制約もあります。
リンの供給経路④:根による可溶化作用
もう一つ紹介されていたのが、
作物の根そのものによる働きです。
作物の根は、
有機酸を分泌することで、
周囲のリンを可溶化し、
吸収しやすい形に変えることがあります。
- 根から有機酸を分泌
- 周囲の鉱物性リンを溶かす
- 可溶性リンとして吸収
という経路です。
主要な経路と、まだ分からない部分
これら4つの経路のうち、
セミナーでは、
- 難溶性リンからの溶出
- 有機物由来のリン
- 菌根菌を介した供給
この3つが、
主要な経路として整理されていました。
一方で、
それぞれの経路が、
- どれくらいの割合で
- どの条件下で
- どれだけ作物のリン吸収に貢献しているのか
という点については、
まだ十分に解明されていない部分が多い、
という説明でもありました。
リンは「分かったつもり」になりやすい元素
リンは、
- 肥料成分としてよく知られている
- 数値で管理されることが多い
ということもあり、
「量さえ見れば分かる」ような印象を持ちやすい元素です。
しかし、
今回の話を聞く限り、
自然栽培におけるリンの振る舞いは、
単純な含有量だけでは捉えきれないように感じました。
次章では、
ここまで見てきたデータや仕組みを踏まえたうえで、
どこまで分かっていて、どこから先が分かっていないのか
その境界線について整理していきます。
データが示す限界と、まだ分かっていないこと
ここまでの章で、
自然栽培の土壌では、
無肥料であってもミネラル含有量が維持されていること、
そして、その背景には
CECやpHといった土壌の性質が強く関わっていることを見てきました。
一方で、
今回のセミナーでは、
「分かったこと」と同時に、
**「まだ分かっていないこと」**についても、
はっきりと区別して語られていました。
この章では、
データが示している範囲と、
そこから先の限界について、
一度整理しておきたいと思います。
少なくとも言えること
まず、
今回示されたデータから、
比較的はっきりしている点を整理すると、
次のようになります。
- 無肥料栽培を30年程度続けても、
土壌ミネラルが一方向に枯渇していく傾向は見られなかった - 栽培年数よりも、
CECやpHといった土壌の性質の方が、
ミネラル含有量に強く関係していた - 土壌中の含有量が低くても、
作物中のミネラル含有量が必ずしも低いとは限らない
これらは、
実測データに基づいた観察結果として、
比較的安心して共有できる部分だと感じました。
しかし、分からないことも多い
一方で、
次のような点については、
まだ十分に分かっていない、
という説明も繰り返されていました。
- 鉱物からの供給が、
どれくらいの速度で、
どれくらいの期間続くのか- リンの供給経路のうち、
どれがどれくらい作物に貢献しているのか- 30年を超えたスケールで見たとき、
同じ傾向が続くのかどうか
特に、
「どこまで持続可能なのか」という問いについては、
現時点では、
はっきりとした答えを出せる段階ではない、
という位置づけでした。
「枯渇しない」と言い切らない理由
ここで印象的だったのは、
セミナー全体を通して、
「半永久的に枯渇しない」といった
強い言い切りが避けられていた点です。
鉱物は、
理論的には有限です。
そのため、
時間スケールをどこまで取るかによって、
評価は変わってきます。
- 数十年のスケールでは問題が見られない
- しかし、数百年、数千年ではどうかは分からない
このように、
時間軸を意識した慎重な整理がされていました。
それでも見えてきた、大きな方向性
ただし、
「分からないことがある=意味がない」
というわけではありません。
今回のデータからは、
少なくとも次のような方向性が見えてきます。
土壌ミネラルの状態は、
「年数」や「投入の有無」だけで決まるものではなく、
土壌が持つ循環の仕組み全体の中で決まっている。
これは、
従来の
「与えるか、与えないか」
という二択の発想とは、
少し異なる視点だと感じました。
次章へ:部分ではなく「全体」を見る
ここまでの章では、
- データ
- 仕組み
- 限界
を、できるだけ切り分けて見てきました。
次章では、
それらをもう一度つなぎ直し、
土壌の中で起きている
「自律的な栄養塩供給」という全体像を、
一段引いた視点から整理していきます。
部分ごとに見てきた話が、
どのようにつながっているのか。
その輪郭を、最後に描いてみたいと思います。
土壌の自律的栄養塩供給という全体像
ここまでの章では、
土壌ミネラルについて、
- 実測データ
- 個別の仕組み
- 分かっていることと、分かっていないこと
を、できるだけ切り分けて見てきました。
この章では、それらをもう一度つなぎ直し、
自然栽培の土壌で起きている栄養塩供給を、全体としてどう捉えられるか
という点を整理してみたいと思います。
「与える」から「回る」へ
慣行栽培では、
栄養塩の供給は、基本的に次のように整理されます。
- 肥料として外部から与える
- 作物が吸収する
- 収穫によって持ち出される
この流れでは、
供給の主体は常に「人の投入」にあります。
一方、
自然栽培の土壌で見えてきたのは、
これとは少し異なる構造でした。
栄養塩は、
外部から与え続けなくても、
土壌の中で循環し、供給されている。
自律的栄養塩供給を支える要素
今回のセミナー内容をまとめると、
自然栽培の土壌では、
次のような要素が組み合わさって、
栄養塩供給が成り立っていると考えられます。
- 土壌鉱物からの、ゆっくりとした溶出
- 有機物の分解による再供給
- 微生物(細菌・菌類)による変換
- CECによる一時的な保持
- pHによって保たれる土壌環境
どれか一つが突出して重要、
というよりも、
これらが同時に働くことで、
供給と消費のバランスが取られている
という印象を受けました。
窒素・リン・ミネラルは別々ではなかった
第9回・第10回を通して印象的だったのは、
窒素、リン、カリウムといった要素が、
それぞれ独立して動いているわけではない、
という点です。
- 窒素は、大気との循環の中で供給され
- リンやミネラルは、鉱物や有機物を介して供給され
- それらすべてが、微生物の活動を通じて結びついている
つまり、
自然栽培の土壌で起きているのは、
個別の栄養素管理ではなく、
土壌全体の循環システムの維持
だと言えそうです。
「無肥料」は結果であって、出発点ではない
ここまでの整理から、
一つはっきりしてきたのは、
自然栽培における「無肥料」という状態が、
単なる条件設定ではない、という点です。
無肥料で成り立っている圃場では、
- 微生物が働ける環境があり
- 分解と供給がつながっており
- 栄養塩が一方的に失われない構造ができている
その結果として、
外部からの投入が必要なくなっている。
つまり、
無肥料は「何もしないこと」ではなく、
循環が自律的に回り始めた状態を指している
と捉える方が、
今回の話には合っているように感じました。
全体像として見えてきたこと
今回のセミナー全体を通して見えてきたのは、
自然栽培の土壌が、
- その場限りの栄養供給ではなく
- 長い時間軸の中で
- 少しずつ均衡を保つシステム
として機能している、という姿です。
もちろん、
すべてが解明されているわけではありませんし、
条件が違えば同じ結果になるとも限りません。
それでも、
「栄養は必ず枯渇する」という前提だけでは、
説明しきれない現象が、
確かに存在していることは見えてきました。
次は「どう感じたか」の話へ
ここまでの章では、
できるだけ個人的な評価を抑え、
構造とデータを中心に整理してきました。
次の最終章では、
今回の第10回セミナーを通して、
自分自身がどんな疑問を持ち、
どのように整理されたのか。
もちまる個人としての受け止めを、
少し言葉にしてみたいと思います。
もちまるの感じたこと(個人的感想として)
今回の第10回セミナーは、
個人的に、ずっと心のどこかで引っかかっていた疑問に、
一つの整理がついた回でした。
前回までで、
窒素については、
大気との循環を通じて供給される仕組みがあることを学びました。
一方で、
リンやカリウム、カルシウム、マグネシウムといった土壌ミネラルは、
空気から供給されるわけではありません。
そう考えると、
作物を収穫し続ける以上、
いずれは土壌中の鉱物が減り、
枯渇していくのではないか。
自然栽培は、どこまで持続できるのだろうか。
この点は、ずっとはっきりしないままでした。
今回のセミナーで示されたデータは、
その疑問に対して、
少なくとも「30年」という時間スケールでは、
明確な枯渇は見られていない、という事実を教えてくれました。
理論的には有限であっても、
実際の圃場では、
鉱物からの供給や、
土壌の保持力、
微生物を介した循環によって、
作物が吸収する量以上の供給が起きている可能性がある。
この点は、
自然栽培を「感覚的な農法」としてではなく、
データと構造のあるものとして捉える上で、
とても大きな材料だと感じました。
もちろん、
「半永久的に枯渇しない」と言い切れるほど、
分かっているわけではありません。
100年、1000年、あるいはそれ以上の時間軸でどうなるのかは、
現時点では誰にも分からないと思います。
ただ、
30年続いて問題が出ていないこと、
さらにその先も継続している事例が存在することを考えると、
少なくとも「すぐに行き詰まる農法」ではない、
ということは言えそうです。
もし、
100年持続するのであれば、
それは一人の人生を超えて、
親から子へ受け継げる農業だと言えます。
仮に50年で何らかの調整が必要になったとしても、
毎年化学肥料を投入し続ける慣行栽培と比べれば、
投入の頻度や規模は、
まったく違ったものになるはずです。
セミナーでは触れられていませんでしたが、
個人的には、
日本に毎年飛来する黄砂や、
火山活動によって供給される鉱物の存在も、
完全に無視できるものではないように思いました。
これらも含めて考えると、
土壌ミネラルの供給源は、
思っているよりも多層的なのかもしれません。
今回の話を通して、
自然栽培とは、
「何も入れない農法」ではなく、
土壌の中で起きている循環が、自律的に回る状態をつくること
なのだと、あらためて感じました。
肥料を入れるか、入れないか。
多いか、少ないか。
そうした二択ではなく、
土壌がどのような状態で、
どのような循環を持っているのか。
その全体像を見ながら、
長い時間軸で向き合っていく農業。
今回の第10回は、
自然栽培をそうした視点で捉え直す、
一つの区切りになる回だったように思います。
▶ 次回レポート
第11回「自然栽培の現状と未来。経営の視点から持続可能性を学んだ日」
第10回では、
無肥料でも土壌ミネラルが枯渇しない可能性
長期無肥料圃場の実測データが示す傾向
慣行栽培と自然栽培におけるミネラル含有量の違い
CECやpHといった土壌特性が果たしている役割
リンやカリがどのように供給されているのかといった点について、
ミネラル循環という視点から、
自然栽培土壌の仕組みを整理しました。前回の内容を通して、
自然栽培では、「肥料を入れない=いずれ枯渇する」
という単純な見方では捉えきれない、
土壌内部の循環が働いている可能性が見えてきました。では、その仕組みが理解できたとして、
次に浮かんでくるのは、
もっと現実的な問い ではないでしょうか。自然栽培は、
実際の農業として成り立つのか。
仕事として、経営として、
本当に続けていくことができるのか。次回・第11回では、
日本農業の現状と収益構造
自然栽培と慣行栽培の生産コストの違い
規模拡大による経費削減の効果
自然栽培米の価格帯と販売実態
収量と価格を踏まえた収益シミュレーション
食味や加工適性といった付加価値の意味といった点を手がかりに、
自然栽培が経営的に持続可能な農業になり得るのか
という問いに向き合っていきます。自然栽培を、
思想や理想としてではなく、
「続けられる農業の一つの選択肢」として捉え直す回です。▶ 第11回のレポートを読む
https://sanseitohow.com/natural-farming-sustainability-management-11/
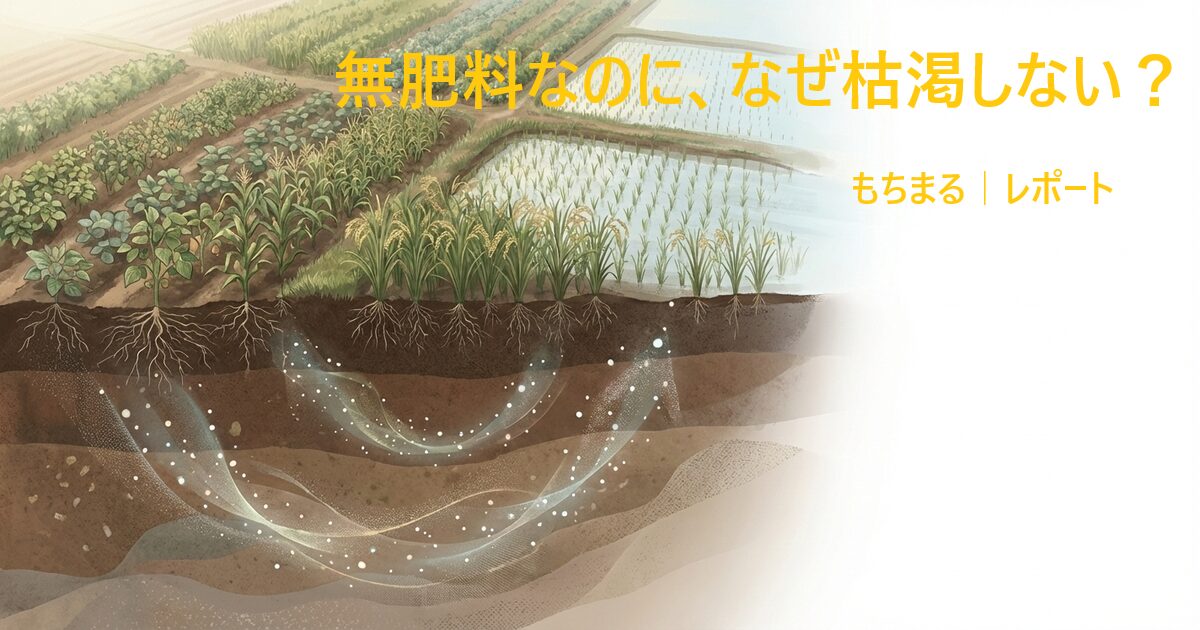


コメント